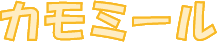|
認知症の方との暮らしの中で、「さっきも言ったのに…」と同じことを何度も尋ねられる経験は、多くのご家族が直面する場面です。そのたびに根気よく答えるのは大変で、ついイライラしてしまうこともあるかもしれません。今回は、記憶障害によって同じ質問を繰り返す方への理解を深め、より良い接し方のヒントをお伝えします。
■接し方の基本
認知症、特にアルツハイマー型認知症などでは、新しいことを記憶する脳の「海馬」という部分がダメージを受けることがあります。そのため、本人にとっては、質問したこと自体、そして聞いた答えもすぐに忘れてしまい、何度聞いても「初めて聞いた」という感覚なのです。これは、決してわざと困らせようとしているわけではありません。むしろ、その背景には「今、何時だろう?」「今日の予定は何だったかな?」といった純粋な疑問や、状況が分からず不安な気持ち、あるいは、誰かと話したい、関心を持ってほしいという思いが隠れていることもあります。
このような状況で、「何度も言わないで!」「さっきも言ったでしょ!」と強く否定したり、無視したりするのは避けたい対応です。本人はなぜ怒られているのか理解できず、ただ傷ついたり、不安が増したりするだけです。時には、「この人は意地悪だ」といった被害的な感情を抱き、介護者への不信感につながる可能性もあります。大切なのは、まず本人の言葉を否定せず、「そうなんだね」「気になるんだね」と受け止め、その奥にある不安な気持ちに寄り添う姿勢です。安心感を与える言葉かけが、信頼関係を築く第一歩となります。
■具体的な対応例
同じ質問が繰り返される時、言葉だけで対応しようとすると、お互いに疲弊してしまうことがあります。そこで、以下のような具体的な工夫を取り入れてみましょう。
まず、視覚的な情報を活用する方法が有効です。例えば、「今日の予定」や「次の食事の時間」などを紙に書いて、本人の目につきやすい場所に貼っておくのです。「10時にデイサービスに行きます」「12時にお昼ご飯ですよ」といった具体的なメモは、口頭での説明よりも記憶に残りやすく、本人が自分で確認できる安心感にもつながります。時計やカレンダーも、すぐに見える場所に置くと良いでしょう。デジタル表示が分かりにくい場合は、針のあるアナログ時計を選ぶなど、本人に合ったものを選んでください。
また、対応する際の環境も大切です。テレビの音や周りの人の話し声が大きい場所では、話が聞き取りにくく、内容も理解しづらくなります。可能であれば、静かな場所に移動し、本人の正面に座って、目を見てゆっくり話すように心がけましょう。
さらに、言葉でのコミュニケーションだけに頼らず、五感に働きかけるような関わりも効果的です。例えば、一緒に散歩に出て季節の花を見たり、簡単な料理を手伝ってもらったり、好きな音楽を聴いたりするなど、本人が心地よいと感じる活動を通して、不安な気持ちを和らげ、穏やかな時間を作ることを意識してみましょう。
■より良いかかわり方のヒント
繰り返される質問の背景には、単なる記憶障害だけでなく、本人が抱える様々な思いや状況が影響している場合があります。より良いかかわり方を見つけるためには、表面的な言動の奥にあるものに目を向けることが大切です。
例えば、「どうしていいのか分からなくて不安」「自分の居場所がないように感じる」「誰かの役に立ちたい」といった満たされない思いが、質問という形で表出しているのかもしれません。あるいは、痛みやかゆみ、便秘、夜眠れないといった身体的な不調が、落ち着かない気持ちを引き起こしている可能性も考えられます。「何か気になることがあるの?」「ゆっくり話を聞かせてね」と、本人の気持ちや体調に変化がないか、普段の様子を注意深く観察し、話に耳を傾けてみましょう。
また、本人が安心して過ごせる環境かどうかも見直してみましょう。使い慣れたものが近くにあるか、自分のペースでやりたいことができる環境か、といった点も重要です。本人の性格やこれまでの生活歴、大切にしてきた価値観などを理解しようと努めることが、その人らしい穏やかな生活を支える鍵となります。「もっと私に関心を持ってほしい」「家族と話したいけれど、何を話せばいいか分からない」といった、言葉にならない本人のサインに気づくことができるかもしれません。

認知症の方が同じことを何度も聞いてくるのは、記憶障害という症状によるものであり、不安の表れでもあります。対応するご家族にとっては根気のいることですが、否定せずに受け止め、安心できる言葉や環境を提供することが大切です。完璧を目指す必要はありません。ご自身の心身の健康も大切にしながら、少しずつ、その方とのより良いコミュニケーションの方法を見つけていきましょう。(スタッフ:たか)
|