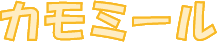|
高齢化が急速に進む現代社会において、認知症はもはや他人事ではありません。厚生労働省の発表によると、2025年には65歳以上の高齢者の5人に1人が認知症になると推計されており、その数は増加の一途をたどっています。認知症は早期発見と早期対応によって、進行を遅らせ、生活の質を維持できる可能性があります。今回は、介護をされているご家族様に向けて、主な認知症の種類と特徴について紹介し、ご家庭でどのように対応できるかを考えます。
■身近な人がかかることも? 4大認知症の種類と特徴
認知症とは、様々な原因によって脳の細胞が損傷し、記憶や思考力、判断力など認知機能が低下してしまう病気の総称です。単なる物忘れとは異なり、生活に支障が出るレベルの症状が現れます。認知症の原因となる病気は数多く存在しますが、中でも患者数が多い代表的な4つのタイプについてご紹介します。
・アルツハイマー型認知症
認知症の中で最も患者数が多いのが、このアルツハイマー型認知症です。脳に「アミロイドβ」という異常なたんぱく質が蓄積することで、神経細胞が徐々に壊れていくことが原因だと考えられています。初期症状としては、物忘れが目立つようになります。昨日の夕食の内容を忘れてしまったり、約束をすっぽかしてしまう、といったことです。進行するにつれて、時間や場所がわからなくなったり、家族の顔さえも分からなくなってしまうこともあります。
・血管性認知症
脳梗塞や脳出血などによって脳血管が損傷し、脳細胞に栄養や酸素が行き渡らなくなることで発症します。症状は脳血管が詰まった場所や範囲によって異なりますが、アルツハイマー型認知症と異なり、比較的早期から判断力や注意力の低下が見られる点が特徴です。また、手足の麻痺や言語障害などを伴うこともあります。
・レビー小体型認知症
脳内に「レビー小体」と呼ばれる異常なタンパク質が蓄積することで発症します。初期症状として、ありありとした幻視や睡眠中の異常行動(寝言、大声、暴力など)が見られることが特徴です。また、パーキンソン病に似た症状(歩行障害、動作緩慢、筋肉のこわばりなど)が現れることもあります。症状は日によって変動しやすく、意識がはっきりしている時と、ぼーっとしている時を繰り返すこともあります。
・前頭側頭型認知症
脳の前頭葉と側頭葉が萎縮することで発症します。他の認知症と比較して若年期に発症するケースが多く、性格変化や行動異常が目立ちます。例えば、周りの人に無関心になったり、反社会的な行動をとってしまうことがあります。また、同じ行動を繰り返したり、特定のものへの執着が見られることもあります。
■「いつもの行動」に注意! 4大認知症の見分け方
2認知症の初期症状は、加齢による物忘れと非常に似ており、見分けることが難しい場合も多いです。しかしながら、早期発見と早期治療開始が進行を遅らせるためには、ご家族による日頃からの観察が重要になります。下記は、認知症のサインとして注意すべき点です。「いつもの行動と違う」と感じたら、早めに医療機関への受診を検討しましょう。
・物忘れ:同じことを何度も聞いてきたり、置き場所を忘れることが増えます。
・時間や場所の感覚が曖昧になる:日付や曜日が分からなくなったり、自宅周辺で迷子になります。
・判断力の低下:お金の管理が難しくなったり、不適切な服装をするようになります。
・感情の起伏が激しくなる:些細なことで怒りっぽくなったり、急に泣き出すようになります。
・興味や関心がなくなる:趣味や外出など、以前は好きだったことに対する意欲がなくなります。
・日常生活動作の困難:着替えや食事、入浴など、身の回りのことが一人でできなくなります。
■認知症と向き合うために。 ご家族様ができること
認知症と診断されると、ご本人様はもちろんのこと、ご家族様も大きな不安や戸惑いを感じると思います。しかしながら、認知症は決して恥ずべき病気ではありません。正しく理解し、適切な対応をすることで、ご本人様が穏やかに過ごせるようサポートすることができます。
・ご本人様のペースに寄り添う:認知症の方は、自身の状況を理解することに不安や混乱を感じていることがあります。焦らず、ゆっくりとコミュニケーションを取り、安心感を与えることが大切です。そして、ご本人様の意思を尊重し、できることはご本人様にしてもらうように心がけましょう。
・環境調整:転倒防止対策や、分かりやすい収納にするなど、安全で過ごしやすい住環境を整えましょう。また、生活リズムを整え、規則正しい生活を送れるようにサポートすることも大切です。例えば、毎日決まった時間に起床・就寝するように促したり、日中は適度な運動や活動を取り入れるようにしましょう。
・地域との繋がりを大切にする:地域包括支援センターや認知症カフェなどを利用し、社会との繋がりを維持しましょう。他の認知症の方やそのご家族と交流することで、不安や悩みを共有したり、情報交換をすることができます。また、地域のイベントやボランティア活動に参加することも、良い刺激となり、社会との繋がりを保つことができます。
・介護サービスの利用:訪問介護やデイサービスなど、ご家族様の負担を軽減できるよう、適切な介護サービスを検討しましょう。介護のプロのサポートを受けることで、ご本人様もご家族様も安心して生活を送ることができます。また、ショートステイを利用することで、ご家族様が休息を取る時間を作ることもできます。
・情報収集:認知症に関する書籍を読んだり、専門機関のセミナーに参加するなど、正しい知識を身につけるようにしましょう。インターネット上にも多くの情報がありますが、信頼できる情報源を選び、最新の情報を確認することが重要です。特に、公的機関や専門団体が提供する情報は信頼性が高いです。
認知症は、誰にでも起こりうる身近な病気です。ご家族が認知症になった時、ご本人様はもちろんのこと、支えるご家族様への負担も少なくありません。しかし、認知症についての正しい知識と適切な対応によって、ご本人様もご家族様も、穏やかに過ごせる日々を送ることは十分に可能です。介護は長期戦です。一人で抱え込まず、地域や専門機関と連携しながら、ご家族皆様で力を合わせて、認知症と向き合って頂ければと思います。(スタッフ:たか)
|